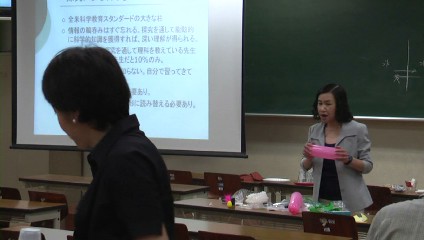
|
 「探究による科学ということで、お話してきたわけですが、今アメリカは探究による科学をもっと進めようという動きがさかんです。 「探究による科学ということで、お話してきたわけですが、今アメリカは探究による科学をもっと進めようという動きがさかんです。
自分で問題を考える。
それから、隣同士で話しなさい。
それから、グループで話しなさい。
皆で発表しなさい。
それで、答えは一つじゃないですね。
いろいろな答えがあるんです。」
|
|
|

|
 「アメリカの授業でよく見られるのは、例えば、数学の授業で余角と補角について、足して180度、足して90度という規則を教え、どんどん問題をやらせるだけというタイプのものです。 「アメリカの授業でよく見られるのは、例えば、数学の授業で余角と補角について、足して180度、足して90度という規則を教え、どんどん問題をやらせるだけというタイプのものです。
で、足して180になるのは余角ですか、補角ですか。余角?
『余角で等しい角はなんだ?』ときく。
90度ですよね。
そういう問題を最後に、これはチャレンジだぞ、と持ってくる。
アメリカの教育というと、日本の人はすごいことをやっているという印象があるかもしれませんが、実は学校教育では反復練習ばかりで、ほとんど概念を教えないのです。
そこへいくと日本は少なくともモデルがあるんです。いい授業をしようと思ったら、指導書の後ろに模範授業が書いてあるから、その通りにやればいい授業ができるし、そういう教員研修を受けている。だからたとえ毎日の授業はそうじゃなくても、ビデオに撮るよって言われれば、模範的な授業が出来る。
アメリカはそれさえもできないんです。」
|
|
|

|
 「去年の秋、私は9月から12月まで、アメリカの公立中学の理科の補助の仕事をしました。
それで、実際に教室の中に入った。びっくりしましたね。すごく悪い。何も教えてない。 「去年の秋、私は9月から12月まで、アメリカの公立中学の理科の補助の仕事をしました。
それで、実際に教室の中に入った。びっくりしましたね。すごく悪い。何も教えてない。
概念理解、つまり子どもが『ああなるほど、そうなんだ』というところには到底いかない。『これはどうしてなるんだ』とも言わない。言葉を覚えるだけ。教科書の後ろに定義が書いてあるから、それを写すだけ。それを丸覚えするだけ。
これがアメリカの教え方。
だから、いろいろな学校があるだろうけれど、基本的に傾向は変わらない。
子どもたちはすごく退屈する。そりゃそうですよね、そんな定義ばっかりで何も教えてくれなかったら退屈します。
定義だけはちゃんとやって、まあ、いい成績を取る。でも、すごく退屈だから何をするかといったら、もっと勉強したい子どもは自分で勉強する。自分で興味があったら、自分で調べないことには、誰も教えてくれない。だからすごく力がつく。
日本は適当によく教えてしまうのかもしれません。だから、学校の勉強をちゃんとやる生徒はすごく達成感があって、その教えられたことを再生産することで、非常にいい評価を得られるし、自分でもやったな、と思ってしまいます。
しかし、自分で問題を考えていないわけです。与えられた問題なのです。自分で興味があって調べた問題じゃない。だからその場が過ぎれば、試験が過ぎれば忘れてしまう。」
|
|
|

|
 【「探究による科学」 【「探究による科学」
○全米科学教育スタンダードの大きな柱
○情報の鵜呑みはすぐ忘れる。探究を通して能動的に科学的知識を獲得すれば、深い理解が得られる。
○しかし、実際に探究を通して理科を教えている先生は少ない。アメリカの新任の先生だと10%のみ。
○先生が探究が何かを知らない。自分で習ってきていない。
○先生が探究を経験する必要あり。
○さらに、教えられるような形に読み替える必要あり。】
 「だからアメリカとは全く違った意味で、日本も探究していかないといけないのではないかと思います。 「だからアメリカとは全く違った意味で、日本も探究していかないといけないのではないかと思います。
自分から問題を選んで『これを解決するためには、自分で考えなきゃいけないんだ』と思って、自ら取り組む姿勢がないと、結局受身の勉強になってしまいます。
なので、アメリカとは違った意味で探究とはどういうものなのかを紹介したいなと思って、今日は用意してきました。」
|
|
|

写真をクリックで動画が見られます(181KB)
|
 「最後に皆さんにやってもらいたいのは、ここに1枚の紙がある。これで橋を作ります。 「最後に皆さんにやってもらいたいのは、ここに1枚の紙がある。これで橋を作ります。
本当だったらちゃんと台を作るんですけど、コップを2つ並べて10cmの隙間を作ります。ここに紙を置けば橋ができます。」
(コップに紙を乗せて橋をかける)
「橋の上に重りを乗せていく。そのとき、橋の作り方に何か工夫をして、なるべく橋が丈夫なように、重さに耐えられるように考えてごらん、というのが、最後の課題です。
今日持ってきた重りは、ボルトとかワッシャーです。
この平な紙の橋に、1枚、ワッシャーを乗せたら、耐えられると思いますか?
科学の大事なところは、自分でそうかな、と疑問に思ったら試すことですね。」
(乗せてみる)
「セーフ。じゃあ2枚は。」
(紙がコップから落ちる)
「だめだったね。」
|
|
|

写真をクリックで動画が見られます(189KB)
|
 「じゃあね、紙の縁を折ります。一番簡単な橋ですね。橋っぽくなりました。これを試してみます。 「じゃあね、紙の縁を折ります。一番簡単な橋ですね。橋っぽくなりました。これを試してみます。
2枚いくかな。(ワッシャーを2枚乗せる)
全然大丈夫ですね。3枚いくかな。(3枚乗せる)
いくねえ。4枚、5枚、6枚。(どんどん乗せていく)
端を折るだけで強度が全然違うわけです。
さっきの1枚の紙じゃだめだったのが、縁を折っただけで丈夫になる理由、説明できますか?
物理を勉強しましたよね。そうしたら物理的に説明できると、納得できることが多いのではないかと思います。私は、自分で物理をやってきたので、物理的説明を自分で持っていることが一つの強みになっています。もっとよく教えられる一つの条件になってるとも思います。
引っ張る力と押す力というのがあって、紙は押す力には強く、引っ張る力には弱い。
縁を折ったことによって、引っ張られる力が縁を押す力になる。押す力になると強くなる。だからただ縁を折り上げただけで、うんと強くなるのです。」
|